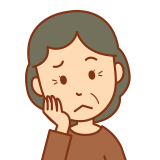
読み聞かせって、本当に意味あるの?
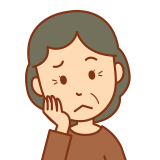
うちの子、全然絵本に興味を示さないんだけど…
そんなモヤモヤ、感じたことはありませんか?
こんにちは、5人の子どもを育てている「ぬいcoco」です。
我が家ではこれまで、正直あまり“絵本の読み聞かせ”に力を入れてきませんでした。
特に上の子たちは、本を読む習慣がほとんどなく、勉強にも少し苦手意識を持っています。
今思えば、もっと小さいうちに「本に親しむ時間」を作ってあげればよかった…と、少し後悔している部分もあります。
でも、だからこそ今、下の子たちには同じ思いをさせたくない。
そう思って、1歳6ヶ月と2歳10ヶ月の子に寝る前の読み聞かせ習慣をスタートしてみました。たった2週間。
でも、子どもたちの反応や言葉の変化、集中力に小さな変化が見え始めたんです。
- 我が家の「寝る前読み聞かせルーティン」の作り方
- 読み聞かせを始めて2週間で現れた1歳&2歳の反応と変化
- 「絵本を聞かない子」への工夫やコツ
- 知育の第一歩としての絵本の使い方
「何から始めればいい?」「本当に意味あるの?」と迷っている方へ、
私の実体験を通して、少しでもヒントや安心を届けられたら嬉しいです。
我が家の読み聞かせルーティンはこうして始まった
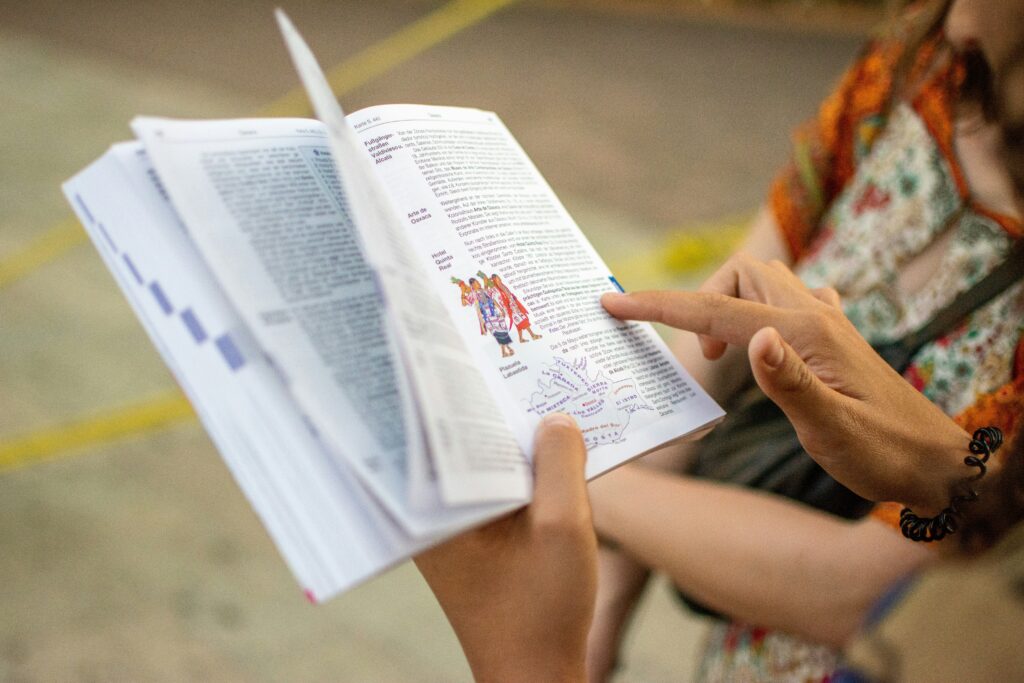
📘きっかけは「上の子の後悔」と「下の子への期待」
上の子たちが小さい頃、私は育児や仕事に追われて毎日バタバタ。
「絵本は大事ってわかってるけど、余裕がない」「読んでも聞いてくれない」そんな理由で、読み聞かせはほとんどできていませんでした。
結果、上の子たちはあまり本に興味を持たず、勉強にも苦手意識が…。
「もっと早くに絵本を読んであげていたら」と後悔することもしばしばでした。
そんな経験をふまえて、今は1歳6ヶ月と2歳10ヶ月の下の子たちにこそ、今できることをやろう!と思い、読み聞かせをルーティン化することに決めたのです。
🕰️毎晩の“寝る前”が絵本タイム
我が家の読み聞かせルーティンはとてもシンプル。
お風呂に入って、ごはんを食べたあとの「寝る前」が絵本タイムです。
子どもたちと布団にゴロンと横になって、
1冊〜多くて5冊までをその日の気分に合わせて選んで読みます。
同じ絵本を何回も読むこともあります。
明かりは少し落として、テレビや音は消しておく。
そうすることで、子どもたちも自然と「絵本の時間モード」に入ってくれます。
✨✨ルーティンにしたことで感じたメリット
読み聞かせを毎晩の習慣=ルーティンにしてみて、一番感じたのは、
“寝るまでの流れに絵本を組み込むこと”が、子どもたちの安心につながるということです。
「お風呂 → ごはん → 絵本 → おやすみ」という毎晩の流れが定着すると、
子どもたちの中でも「絵本を読んだら寝る時間だな」というリズムが自然とできあがっていきました。
また、こんな変化もありました。
- 「寝る前は絵本」が当たり前の流れとして定着した
- 「今日はどの絵本にする?」と子どもが自分から選ぶようになった
- お気に入りの本を繰り返し読むことで、言葉やフレーズを覚えはじめた
最初のうちは、そわそわして途中で立ち上がったり、興味を示さない日もありました。
でも、毎日続けるうちに、絵本の時間が“特別”ではなく“いつものこと”になっていき、反応も少しずつ変わっていったのを実感しています。
💡「読み聞かせ=特別なこと」にしないのがコツ
読み聞かせって、かしこまってやると疲れますよね。
でも、「お風呂・ごはん・絵本・おやすみ」くらいの流れに組み込んでしまえば、がんばらなくても“毎日やれる”仕組みになります。私も最初は「今日は疲れてるし、明日でいいか…」と思った日もありました。
でも、「1冊だけでも読もう」と決めていたおかげで、続けることができました。
2週間で見えた!1歳・2歳それぞれの変化
👶1歳6ヶ月(次女)の変化|“まねっこ”が増えてきた!
読み聞かせを始めたころの次女は、絵本を開いてもページをめくるのが楽しいだけで、話を聞くというより“遊びの延長”という感じでした。
でも、毎日続けていくうちに少しずつ変化が。
- 絵本を見せると、自分から近づいてくるようになった
- 絵本で出てきた「頭」や「目」という言葉をまねして、自分の頭や目を指さしながら見せてくれるようになりました。
- 「もう一回」を覚えた!
言葉が爆発的に増える時期に入ってきたこともあり、
絵と音がリンクする絵本は、まねっこ→発語につながりやすいと実感しました。
👦2歳10ヶ月(三男)の変化|集中力と理解力がアップ!
三男も最初は落ち着きがなくて、
読み聞かせ中に立ち上がったり、おもちゃに気がそれたりしていました。
でも今では、絵本を読み始めると最後までしっかり聞いてくれるように!
- ストーリーの展開に声を出して笑ったり、驚いたり
- 絵本のセリフを覚えて一緒に口にするようになり、言葉を覚えるだけでなく、登場人物への共感や気持ちの表現もできるようになってきました。
- 絵本の内容をそのまま日常でまねするように(例:歯磨き、手洗いがスムーズになった。)
特に、生活習慣に関係する絵本を読んだあとは、
その行動を“遊びのように”まねすることで習慣づけにも役立っていると感じます。
🔄毎日続けることで、“反応が育っていく”感覚
こうした変化は、1日で劇的に変わるものではなく、
**「毎日少しずつ積み重ねたからこそ見えた小さな変化」**だと思います。子どもの反応を見ながら絵本を変えたり、読むテンポを調整したり、
工夫しながら続けることで、読み聞かせが親子にとって心地よい時間になってきました。
実際にハマった!1歳&2歳におすすめ絵本3選
絵本ってたくさんあって、どれを選べばいいのか迷いますよね。
ここでは、実際に我が家の1歳6ヶ月と2歳10ヶ月の子が反応よく楽しんでくれた絵本を3冊ご紹介します。
①『だるまさんが』|からだの動きと一緒に楽しめる!
- 【対象年齢】0歳〜2歳
- 【作者】かがくい ひろし/ブロンズ新社
「だ・る・ま・さ・ん・が…」のリズムに合わせて体を左右に揺らしたり、
「どてっ!」のところで子どもたちが一緒に転がったり、親子で大笑いできる絵本です。
1歳の娘はページをめくるたびに「きゃはっ!」と笑い、
2歳の息子はセリフを覚えて一緒に声に出すように。
言葉のリズム感・身体の動き・まねっこ遊びが自然とできる絵本です。
『いないいないばああそび』|定番だけど何度でも笑える!
- 【対象年齢】0歳〜2歳
- 【作者】きむら ゆういち/偕成社
- 【シリーズ】あかちゃんのあそびえほん
赤ちゃんの大好きな「いないいないばあ」をテーマにした仕掛け絵本。
ページをめくるたびに、いぬさんやねこさんが「いないいない…ばあっ!」と登場します。
1歳の娘は、毎回「ばあ!」のタイミングで笑い、何度も読んで〜と絵本を持ってきます。
2歳の息子は、自分から「ばあ!」と声を出したり、絵本を一緒にめくって楽しんでいます。
繰り返し遊べる内容と、ページごとのリズム感が抜群!
はじめての読み聞かせにもぴったりの1冊です。
『おててがでたよ』|着替えのステップを楽しく伝えられる絵本
- 【対象年齢】0歳〜2歳
- 【作・絵】林 明子/福音館書店
お着替えを嫌がる子におすすめの1冊。
絵本の中で赤ちゃんが「おててがでたよ」「あたまがでたよ」と、服を一つひとつ着ていく様子が描かれています。
1歳の娘は、絵本のセリフをまねして、自分の手を「ここ!」と指差したり、服の袖に手を通すときに「おててでた〜」と喜ぶようになりました。
2歳の息子も、絵本を読んだあとから「自分でやる!」という気持ちが強くなり、着替えの時間が前よりスムーズに。
**ただ読むだけでなく、日常の行動とつながる「体験型絵本」**として、
知育や生活習慣の第一歩にぴったりです。
💡絵本選びのポイント
- 年齢よりも「その子の今の興味」で選ぶのがコツ!
- 同じ本を繰り返し読むことで、言葉や感情が育ちます
- 迷ったときは図書館や立ち読みで“反応チェック”もおすすめ
「なにを読めばいいか迷ってる…」「絵本の反応がイマイチで…」という方も、
まずはこの中から気になる1冊を選んでみてくださいね😊
読み聞かせを毎日続けるためのコツ4つ
読み聞かせは「やった方がいい」と分かっていても、
忙しい毎日の中で**“習慣化する”のは意外と難しい**もの。
私自身、5人の子育ての中で「今日は疲れたから、やめちゃおうかな…」と思う日も何度もありました。
でも、そんな中でも続けられたのは、以下のような工夫があったからです👇
①「寝る前の定番」にして“考えずにできる習慣”にする
- お風呂 → ごはん → 絵本 → おやすみ
という流れを毎日繰り返すことで、自然と読み聞かせが日常の一部に。
「読むか読まないか」ではなく、「今日はどの絵本にする?」という思考に変わるので、
無理せず続けられるコツになります。
② 1日1冊だけでもOK!“完璧を目指さない”
- 読み聞かせ=何冊も・長時間やらなきゃ…と思うと負担になってしまうので、
「1冊だけ読む日」があってもOK! - 疲れている日は短い絵本でも十分。何より「毎日続ける」ことが大切。
③ 子どもが飽きたら絵本を変えてみる
- 何度も読んでいるうちに飽きてしまうこともありますよね。
そんなときは図書館を活用して、季節やブームに合わせた絵本を試すのがおすすめ。 - 特に乗り物、動物、食べ物など、“今のハマり”に合わせると集中してくれやすいです。
④「聞いてくれない日」も気にしない
- 絵本を読んでも走り回ったり、聞いていないように見える日もありますが、
実は耳ではちゃんと聞いていたり、あとで再現していたりすることも。
「聞いてないな」と感じても、焦らず・怒らず・あきらめず、
その日のペースでOK!と気楽に構えるのが長続きの秘訣です。
まとめ|読み聞かせは「親子の時間」と「学びの入口」
たった2週間の読み聞かせ習慣でも、
1歳・2歳の子どもたちに確かな変化が見えてきたことに、私自身もびっくりしています。
絵本を読むことで、
- 言葉をまねしたり
- お話を覚えたり
- 感情を表現できるようになったり
そんな小さな成長が、親として何よりもうれしい瞬間でした。
でも一番よかったのは、
「絵本を読む=親子のコミュニケーション時間」になったこと。
忙しい毎日でも、たった5分でも一緒に笑って、感じて、つながれる。
それだけで、子どもにとっても安心で大切な時間なんだと思います。
🌱今からでも遅くない!まずは“1日1冊”から
もし「今からじゃ遅いかな」「うちの子、聞いてくれないし…」と迷っているなら、
まずは短い絵本を1冊読むところから始めてみてください。
子どもが絵本に集中できなくても、立ち歩いてもOK。
「聞く力」も「楽しむ力」も、毎日の積み重ねで少しずつ育っていきます。
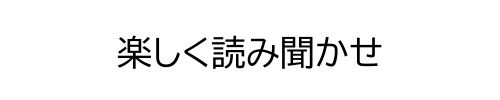

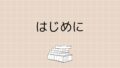

コメント